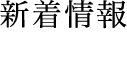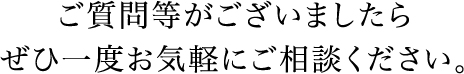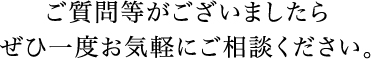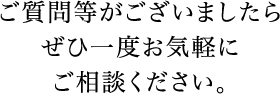盆提灯とは? 選び方や飾り方について
盆提灯

盆提灯に込められた意味とは
ほのかな灯りが幻想的に揺れる盆提灯(ぼんちょうちん)。
美しい絵柄が描かれたその姿は、仏壇を彩る装飾のひとつのようにも見えますが、
実はお盆の由来と深い関わりを持つ大切な意味があります。
◯ご先祖さまの「道しるべ」
盆提灯は、お盆に帰ってくるご先祖さまの霊が迷わず帰ってこられるように灯す、
いわば「道しるべ」の役割を果たしています。優しく揺れる明かりには、
故人への想いと敬意が込められており、現代においても大切に受け継がれている習慣です。
◯心を込めたお迎えのしるし
単なる飾りではなく、ご先祖さまを丁寧に迎え入れるための心のあらわれとして盆提灯は飾られます。
その灯りは、故人の魂を迎え入れるとともに、家族の絆を再確認する時間でもあります。
盆提灯の用意のしかた・選び方
お盆の時期に飾る「盆提灯(ぼんちょうちん)」には、ご先祖さまの霊をお迎えするという大切な意味があります。
ここでは、盆提灯を用意するタイミングや選び方のポイントをご紹介します。
◯本来は「贈られるもの」だった盆提灯
かつては、初盆を迎える家に親戚や故人と親しかった方が盆提灯を贈るのが一般的でした。
しかし、近年では住宅事情や生活スタイルの変化により、ご家族が自ら用意するケースも増えています。
そのため、贈る側も提灯そのものではなく「御提灯代」として現金を包むことも一般的になっています。
※自分たちで盆提灯を用意する予定がある場合は、
贈ってくださる可能性のある方にあらかじめ伝えておくと、混乱を防げます。
◯飾る際は「2つで1対」が基本
盆提灯は2つで1組(1対)として飾るのが基本です。精霊棚(しょうりょうだな)や
仏壇の前などに1対、2対……と偶数で飾るのが習わしとされています。
かつては、たくさんの提灯が並ぶほど「多くの方に慕われた証」とされていましたが、
近年はスペースの関係などから、1対だけ飾るご家庭も増えています。
数に厳密な決まりはないため、無理のない範囲で選びましょう。
◯デザインは故人の趣向や部屋に合わせて
一般的には、家紋入りや菊・萩・桔梗など秋の草花をあしらった柄の盆提灯が多く見られます。
ただし、決まりは厳しくないため、故人の好みや、
お部屋の雰囲気に合ったデザインを選んでも差し支えありません。
最近では、現代住宅にも合うモダンな提灯も登場しており、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。
お盆を迎えるご家族の想いに寄り添い、
伝統を大切にしながら現代の暮らしにもなじむ盆提灯を多数ご用意しております。
初めての方も、どうぞ「杉原仏檀店」をお気軽にご相談ください。